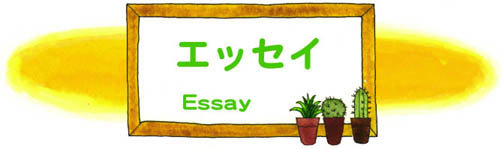
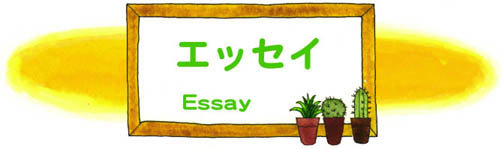
●●● ブリキの金魚 ●●●
おもちゃ屋にしても駄菓子屋にしても、子ども相手の商売というのはシビアだな、と思う。大人から見ると、「夢を売る商売」と気楽に映るのだが、現場は決して生優しくない。十円、百円といった少ない利鞘(りざや)を、これまた十円、百円といったお金しか持たない子どもたちからひねり出そうというのだ。シビアで当然だ。
駄菓子屋に群がる子どもたちの輪から離れて、ひとりポツンと立っているお金のない子。可哀相だな、と思って情けを掛ければ、僕も私もと、その回りの子どもたちが団子状態で襲ってくる。「この子だけ」なんてことをうっかり口にしようものなら、「あの店は贔屓する」と総スカンを喰らってしまう。だから、
「金のない子は買えないよ」
という意志表示は、最初からはっきりしている。
これは、四、五才の頃の話だが、今でもよく覚えている。屋台の焼き芋屋が近くに来た。
「やきぃもぉ、焼き芋!」
という売り声が、焼き芋のいい香りに乗って近づいて来た時、私はお隣りのトコちゃんとふたりで、道にしゃがんで蝋石で絵を描いていた。トコちゃんは、私よりもひとつ年上の女の子だ。
「焼き芋、食べたい」
彼女がいう。
「私も、食べたい」
ふたりは蝋石を放り出すと、それぞれの家に駆け込んだ。トコちゃんは百円、私は五十円をもらい、それを握りしめて飛び出すと、焼き芋屋を追いかけた。焼き芋屋の親爺さんは、私たちの声にリヤカーを停めた。
「焼き芋、ください」
トコちゃんが百円を突き出す。
親爺さんは石焼き釜の木の蓋を取って、吊り計りの上にひとつ、焼き芋をのせた。
「はい、これがちょうど百円のね」
そういうと、それを新聞紙を張り合わせて作った、簡単な袋に入れて手渡した。
私も胸を躍らせて五十円を突き出す。親爺さんは、私の手の中の五十円を見ると、
「五十円じゃ、焼き芋は買えないよ」
とあっさり言い捨てて、さっさと釜の蓋を閉めてしまった。そして振り向きもせずに去って行った。
トコちゃんは、私の方を振り返りながら気の毒そうな顔をする。だが、いうことはきつかった。
「百円、もらってくればよかったのに。百円もないの?」
半分あげようか、なんていうことは、間違ってもいわない子だ。
私の涙腺がジンジンと痛みだした。これは涙が出る直前の合図。でも、何とかこらえて家に駆け込んだ。ドアを閉めた途端に、ぼたぼたと涙がこぼれた。
当時、我家は決して裕福ではなく、その五十円だって、気兼ねしながらねだったものだったのだ。もっと頂戴とは、とてもいえない。
「どうしたの、泣いて? 焼き芋屋さん、行っちゃったの?」
母はアイロンをかけていた。
その膝に顔を埋めて、私は泣いた。私は絶対に声を出して泣かない子どもだった。
「ご、ご、五十円じゃ、……や、焼き芋、買えないって……」
しゃくり上げているから、どもってしまう。母は、黙って頭を抱き寄せてくれた。
気配を感じた父もやって来て、私の泣く理由を尋ねる。
「こんな小さな子どものことじゃないか、どうしてひとつの芋を半分に割ってでも売ってやらないんだ!」
怒って立ち上がろうとする父の腕を、母が掴んで止めた。
この時のことを、どうしてこんなに鮮明に覚えているのだろう。
焼き芋屋の態度。トコちゃんの言葉。自分の差し出したお金で、欲しいものが買えなかったという事実。もしかしたら、最初に経験した「屈辱」だったのかもしれない。
この話、ブリキの金魚とは、何の関係もないけれど。
(2000年10月の個展『心の図鑑』より)
