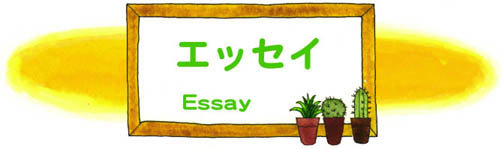
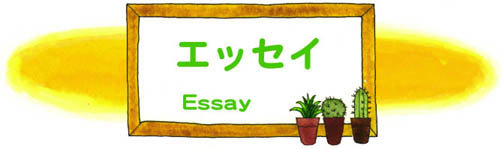
●●● 姉さん人形 ●●●
留学三年目の冬、私は毎日、図書館か自室のどちらかに籠もって卒論を書いていた。
外は雪。毎日、雪。気温は零下二十度。気が滅入る日々だった。
その大学は、猛烈な勉強量が求められる学校だったから、毎年、何人もの学生がノイローゼになって、この辛い冬場に落伍したり、自殺未遂をやらかしたりする。そういう問題を起こすと即座に退学だ。
私も、自分の学力の無さやら、人恋しさやら、卒論のプレッシャーに押し潰される直前だった。そんなことを知ってか知らずか、クラスメートのひとり、ナンシー・アイオットが声を掛けてくれた。
「週に一度、我が家へいらっしゃいよ。一緒に夕飯を食べましょう」
クラスメートといっても、私より二廻り近くも年上の女性だ。レストランを経営していて、息子が三人いる。彼女のレストランは、学校から半時間ほど行った避暑地の、観光スポットにあって繁盛していた。朝食と昼食だけを出す店で、5月から10月までの半年間だけ経営している。冬場は、時間を自由に使えるわけだ。ご主人さまは趣味と実益を兼ねて工房で家具を作り、彼女は大好きなフランス語の勉強に身を入れる。大学院へ戻ったのも、そのためだった。
私が初めて訪ねて行った時、長男はすでに大学へいっており、次男も来年は大学生という立派な青年で、遅れて生まれた三男だけが、まだ可愛らしい小学生だった。
彼女の料理は素晴らしい。毎回、スープ、サラダ、メインディッシュの他に、フランスパンやデザートのお菓子まで焼いて待っていてくれた。料理好きの私は、そのひとつひとつの作り方を習うのが嬉しかった。高価な食材はひとつもないが、どれもこれも心がこもっていて、彩
りも美しい。テーブルを綺麗にセッティングして、ご馳走を並べて、蝋燭をともして席に着く。隣りの人と手をとりあって輪を作り、食前の祈りを捧げる。彼らは敬虔なクリスチャンだ。
この団らんが、どれ程の元気を私に与えてくれたことだろう。 週に一度の、雪の中の訪問が、どれ程の精神安定剤になったことだろう。
彼女たちにとっては日常の団らんに過ぎなかったかもしれないが、異国にひとり居た私にとっては、珠玉
のひとときだった。本当に彼女たちのお陰で、無事に卒論を書き上げ、卒業できたと思っている。
この夕食会は、三、四ヶ月続いた。私が材料を持ち込んで、和食を作ったことも数回あった。ナンシーは、小柄だが、全身からプラスのエネルギーが発散しているような女性だ。明るく、楽天的で、よく笑う。彼女からは、たくさんのことを学んだ。一人の女性としても、主婦としても、理想的な生き方をしているように思う。
母親としては、かなり厳しいほうだ。勿論、家族には最大級の愛情を掛けており、また彼らからも絶大な信頼を受けている。
ある夕食会の晩は、バレンタインデーの前日だったように思う。
「今日は、特別な趣向で食事を用意しているんだけれども、菜奈も手伝ってくれないかしら?」
そういわれて出かけてみると、その日のゲストは私ではなくて、息子二人と、そのガールフレンド二人であった。十二才のカップルと、十八才のカップルだ。テーブルも、いつもより念入りにセッティングしてある。
「バレンタインディナーのフルコースを作ってあげるのよ」
彼女はそういって、台所で張り切っていた。ナンシーも、私も、ご主人さまも、今夜は同席しない。子どもたちに花を持たせる夜なのだ。
「菜奈には是非、ウェートレスをして欲しい」
というので、私はレストランで使っている、ウェートレス用のエプロンを付けて、にわかウェートレスになった。
それは、何とも素晴らしい光景だった。蝋燭の灯りがともるいい雰囲気の中で、二組のティーンエイジャーたちが、いつもよりもちょっとお洒落して、母親の作ったご馳走を、お行儀よく食べながら、嬉しそうに笑い合っている。母親は、一番美味しく食べてもらえるタイミングを図りながら、台所で立ち働いている。ダイニングテーブルも、椅子も、父親が作ったものだ。家中に、愛情が満ちていた。
その晩、食事が済んでから、私はみんなに「姉さん人形」の作り方を教えてあげた。わずかな色紙と和紙と爪楊枝で、簡単に可愛い人形が作れるので、彼らは驚いていた。ティーンエイジャーたちも、一生懸命、指先を動かして、小さな人形を幾つもこしらえた。
後日、その姉さん人形を、ひとつずつカードに貼って、バレンタインのカードとしてクラスメイト全員に配った、と聞いて、こちらまで嬉しくなった。
何もかもが温かい、アメリカの田舎の話だ。
ナンシーとは、今でも大親友だ。
息子たちは、みんな立派に育ってしまった。
(2000年10月の個展『心の図鑑』より)
